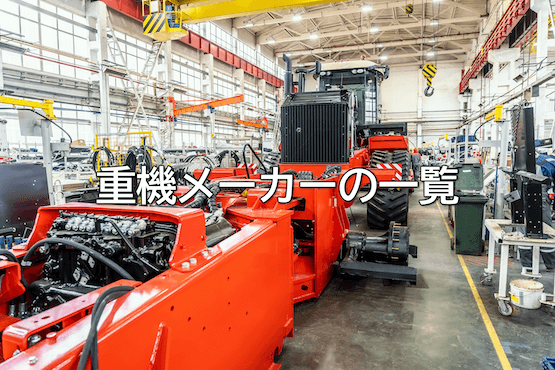スクレーパーとは?種類や用途、資格を解説
スクレーパーとは、土木・建設工事などで活躍する重機の一種です。主に大量の土砂の掘削・運搬・敷ならしなどを行う目的で使用され、大規模な造成工事や道路建設などに不可欠な重機となっています。
本記事では、スクレーパーの基本情報から種類、用途、導入時に必要な資格まで詳しく解説します。スクレーパーの導入を検討している建設事業者の方に向けて、わかりやすく要点を整理しました。スクレーパーの導入をスムーズに進めるための参考としてご活用ください。
目次
スクレーパーとは?

スクレーパーは、掘削、積込み、運搬、土の排出、地ならしといった一連の土工作業を1台でこなせる重機です。土木工事や造成工事などの現場で広く活用されています。
現行のスクレーパーは、電子制御エンジンの搭載や排ガス規制への対応により、環境性能が向上しています。特に日本国内では、厳しい排ガス規制をクリアするための改良が進められていますが、海外でも同様の動向が見られます。
また、オペレーターの負担を軽減する自動制御機能や低公害・低騒音設計が採用され、安全性と快適性が向上しています。
加えて、オートマチックトランスミッションを導入することで、レバー1本で前後進や速度調整ができるなど、操作性も大きく向上しています。
スクレーパーの用途
スクレーパーは、高い土地を削り、低い場所を埋める作業に適した重機です。したがって、宅地造成、工場敷地の整備、ゴルフ場の造成、道路建設など、土地の形状を大規模に整える現場で活躍しています。
スクレーパーは、土砂の掘削・積み込み・運搬を1台で行うことができ、1km程度の短距離輸送にも対応可能です。そのため、大規模な整地作業が必要な現場では、作業の効率化に大きく貢献します。
しかし、近年、日本国内では大規模な造成工事の減少により、スクレーパーの需要が低下しているとも言われています。加えて、スクレーパーは車両のサイズが大きく、公道を自走することが難しいため、トレーラーなどを利用した輸送が必要になる場合があります。
この輸送コストや手間が導入のハードルを上げる要因となることも考えられます。一方で、新興国ではインフラ整備や都市開発の進展に伴い、スクレーパーの需要が高まっているとも報告されています。
以下の記事では、重機全般について、種類や役割、用途、取得が求められる資格とともにわかりやすく解説しています。スクレーパーをはじめとする重機の導入・活用を検討している場合には併せてご覧ください。
スクレーパーの種類

スクレーパーには、大まかに以下の3種類が存在します。
- 被けん引式スクレーパー(キャリオールスクレーパー)
- 自走式スクレーパー(モータースクレーパー)
- スクレープドーザー
それぞれの重機に見られる特徴について、順番に詳しく解説します。
被けん引式スクレーパー(キャリオールスクレーパー)
被けん引式スクレーパーは、トラクターでけん引して使用するタイプのスクレーパーです。動作の仕組みによって、ワイヤロープを使う「ケーブル式」と、油圧シリンダーで作業を行う「油圧式」の2種類に分類されます。
現在主流なのは油圧式で、ウインチを搭載する必要がなく、操作がシンプルで扱いやすいのが特徴です。また、履帯式(クローラー)トラクターでけん引するため、不整地や勾配のある地形や軟弱地でも安定して作業できます。
また、近年では超ワイド低圧タイプのキャタピラーを装着したモデルも開発されており、これまで難しかった柔らかい地盤での作業にも対応可能となりました。そのため、従来よりも幅広い現場での活用が期待されています。
自走式スクレーパー(モータースクレーパー)
自走式スクレーパー(モータースクレーパー)は、エンジンを搭載し、自走できるスクレーパーです。作業の仕組みは、被けん引式スクレーパー(キャリオールスクレーパー)とほぼ同じですが、エンジンを備えていることでより効率的な作業を可能としています。
駆動方式により、以下の3つのタイプに分類されます。
- シングルエンジン式(前輪駆動)
- ツインエンジン式(タンデムエンジン式:前後輪駆動)
- エレベーティングスクレーパー(積込部分にエレベーター装置を搭載)
被けん引式スクレーパーと比べて走行速度が速く、長距離の運搬に適しているのが大きな特徴です。そのため、広範囲の土砂運搬が必要な現場で活躍しています。
自走式スクレーパーの機種の一例として、キャタピラー(CAT)社の「623K」や「627K」があります。このうち627Kはオープンボウルスクレーパーに分類され、様々な資材に対応できる自動積載のプッシュ式積載運搬機械として活用されています。
スクレープドーザー
スクレープドーザーは、スクレーパーの掘削・運搬機能に加え、ブルドーザーの押土(おしど)・整地機能を兼ね備えた重機です。
スクレーパーのように「ボウル」を使用して土砂を掘削・運搬できるだけでなく、ブルドーザーのように前方の「ブレード」を活用して地面をならしたり、押し広げたりすることが可能です。そのため、一台で掘削・運搬・整地の3つの工程を効率的に行うことができます。
スクレープドーザーは、大まかに以下の流れで作業を行います。
- 前方のブレードで土砂を押し広げる(整地作業)
- ブレードを持ち上げ、ボウルを下げながら前進し、土砂を掘削・積み込みする(掘削・運搬作業)
- ボウル内の土砂を目的地で排出し、再びブレードを使って地面を均す(仕上げ整地作業)
この仕組みにより、50m〜150m程度の中距離の掘削・運搬や整地作業に適しており、狭い現場でも作業が可能です。特に、造成工事や道路工事において高い作業効率を発揮します。
スクレーパーの免許・資格
スクレーパーの操作・運転にあたって取得が求められる免許・資格は、以下のとおりです。
| 必要な免許・資格 | |
|---|---|
| 操作 | 車両系建設機械運転者 |
| 公道の走行 | 大型特殊自動車免許 |
車両系建設機械運転者
スクレーパーが属する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)を操作するために求められる資格は、機体重量によって以下の2種類に分かれます。
| 機体重量 | 資格の名称 |
|---|---|
| 3t以上 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 |
| 3t未満 | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 |
技能講習および特別教育には、いずれも学科と実技があります。また、技能講習の受講時間については、現在保有している資格や業務経験などによって異なるのでご注意ください。
車両系建設機械について、詳しくは以下の記事で解説しています。
大型特殊自動車免許
スクレーパーは「大型特殊自動車」に分類されるため、公道を走行させるには「大型特殊自動車免許」が必要です。ただし、作業現場内のみで使用する場合は、公道走行を前提としないため、この免許は不要です。
大型特殊自動車免許の取得方法には、以下の3つがあります。
- 教習所に通う方法
- 試験場で直接試験を受けて合格する方法(いわゆる「一発試験」)
- 合宿免許に参加する方法
どの方法を選ぶかによって、費用や取得にかかる日数が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。なお、受験資格は18歳以上とされています。
以下の記事では、車両系建設機械運転者や大型特殊自動車免許をはじめ、様々な重機の取り扱いにあたって必要となる免許・資格について詳しく紹介しています。
スクレーパーの免許・資格について理解を深めたい場合や、スクレーパー以外の重機の導入も検討している場合は、併せてご覧ください。
まとめ
スクレーパーは、大規模な土工工事や造成工事において土砂の掘削・運搬・敷ならしを一台で行える効率的な重機です。特に、長距離の土砂移動が必要な現場では、その高い作業能力を生かして施工時間を短縮できます。
スクレーパーを導入する際には、作業現場の特性に合った機種選定が重要です。また、操作・運転には免許・資格が必要となるため、免許・資格の取得や適切なオペレーターの確保も検討しなければなりません。
スクレーパーの効果的な活用により、工事の効率化やコスト削減が期待できるため、用途や種類を正しく理解した上で、導入のメリットを最大限活用しましょう。