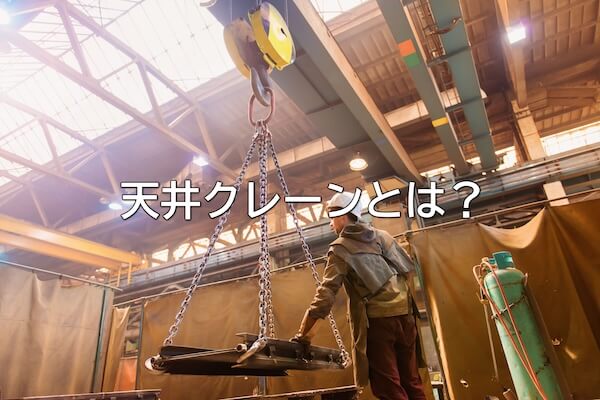普通免許で乗れるトラックは何トン?取得時期ごとに一覧で解説
「2tトラックは普通免許で運転できる」と言われることがありますが、実際には“2tトラック”という名称は最大積載量を意味しており、運転可否は車両総重量や免許取得時期によって異なります。そのため、必ずしも全ての2tトラックが普通免許で運転できるわけではありません。
2007年と2017年に行われた道路交通法の改正により、普通免許で運転できる車両の基準は段階的に厳しくなっています。そのため、以下の点に気をつける必要があります。
- 「2tトラック=普通免許で乗れる」とは限りません
- 自分の免許で運転できるトラックの条件を十分に確認する
本記事では、普通免許で乗れるトラックの条件を「免許の取得時期別」にわかりやすく一覧でまとめました。また、以下の点についても詳しく解説しています。
- なぜ免許の条件が変わったのか
- 自分の免許でどの車両を運転できるのかの判断方法
- よくある誤解や注意点
普通免許とその他の運転免許(準中型、中型、大型免許)との違いも紹介しますので、仕事でトラックを運転する場合、免許の取得や更新を考えている場合はぜひご参考ください。
目次
普通免許で乗れるトラックとは?

まず、普通免許で乗れるトラックの条件を確認しておきましょう。現在の道路交通法において、普通免許で運転できる車両には以下の制限があります。
- 車両総重量:3.5t未満
- 最大積載量:2t未満
- 乗車定員:10人以下
これらの基準は、2017年3月12日の道路交通法改正によって導入されました。安全性の向上や、運転スキルに応じた車両制限を目的としています。過去にはより大型の車両まで普通免許で運転できましたが、事故の増加や社会的要請を背景に、段階的に制限が厳しくなった経緯があります。
原則として、これら3つの条件すべてを満たしているトラックであれば、普通免許で運転可能とされています。ただし、車両の仕様変更や構造の追加(クレーン付きなど)によって車検証上の重量が変わっている場合もあるため、実際の車検証で確認することが重要です。
ただし、上記は2017年3月12日以降に普通免許を取得している場合の基準です。それ以前に普通免許を取得している場合、車両総重量と最大積載量がより大きなトラックを運転できます。つまり、「自分が普通免許をいつ取得したのか」によって、乗れるトラックの条件が異なるのです。
また、注意が必要なのが「2tトラック」という言葉です。一般的に「最大積載量2tのトラックは普通免許で運転できる」と思われがちですが、実際には“2tトラック”という呼び方は積載量を基準とする一方、運転可否は車両総重量ベースで判断されるため、混同を招きやすい表現です。
2tトラックと呼ばれていても、オプション装備などにより総重量が3.5tを超え、現行の普通免許では運転できないケースもあるため、注意が必要です。
したがって、「2tトラック=普通免許で乗れる」とは限らない点に十分注意しましょう。
「車両総重量」と「最大積載量」の違い
車両総重量と最大積載量は混同されがちですが、意味が異なる言葉です。自分が持つ免許の範囲内で適切に運転するためにも、2つの言葉の違いを正しく理解しておきましょう。
最大積載量とは、トラックやダンプなどの車両が一度に安全に積載できる荷物の重量上限のことです。一方で、車両総重量は、「車両本体の重さ」に「定員全員が乗車した場合の体重(1人あたり55kg)」と「最大積載量(荷物の重さ)」を合計した重さを意味します。
つまり、車両総重量の中に最大積載量が含まれるという関係性です。車両総重量や最大積載量について、より詳しく知りたい場合は、以下の関連記事も併せてご覧ください。
車両重量と車両総重量の違いとは?免許や車検にも関わる基本知識
最大積載量とは?計算方法・車両総重量との違いを解説
普通免許で乗れるトラックは取得時期によって異なる
普通免許で乗れるトラックの条件は、免許を取得した時期によって大きく異なります。これは、2007年と2017年に実施された道路交通法の改正によるものです。
かつては普通免許でも比較的大型のトラックを運転できましたが、交通事故の増加や運転スキルの問題などを背景に、段階的に運転できる車両の条件が厳しくなっています。その結果、「同じ普通免許でも、取得日が異なれば運転できる車両の範囲が異なる」という状況が生まれています。
自分の免許の取得時期を確認する方法
普通免許には、取得時期に応じて以下の3つの種類があります。
- 平成19年(2007年)6月1日以前:中型8t限定付きの普通免許
- 平成19年6月2日〜平成29年(2017年)3月11日:準中型5t限定付きの普通免許
- 平成29年3月12日以降:現行の普通免許(これまでで最も条件の範囲が狭い)
自分がどの種類に該当するかは、運転免許証にある「免許の条件等」の欄の記載内容で確認できます。
- 「中型車は中型車(8t)に限る」:中型8t限定付きの普通免許
- 「準中型車は準中型車(5t)に限る」:準中型5t限定付きの普通免許
- 上記の記載がない:現行の普通免許
また、普通免許の取得日からでも、自分の普通免許の種類を把握できます。免許取得日は、運転免許証の左下にある「取得日」の欄で確認できます。この欄には、取得した免許の種類ごとに日付が3行で記載されており、普通免許を含む複数の免許を保有している場合、それぞれの取得日が分かれて表示されます。
多くの場合、2行目に「他」と表示されている欄が普通免許の取得日となっていることが一般的です。ただし、免許の追加取得や再発行の有無によって表示形式が異なるケースもあるため、正確に把握したい場合は、最寄りの警察署や免許センターに確認すると安心です。
取得時期別|運転できる車両の範囲(車両総重量・最大積載量)
下表に、自動車運転免許の取得時期別に、運転できる車両の条件をまとめました。
| 取得時期 | 免許区分 | 車両総重量 | 最大積載量 | 主な受験資格 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年6月1日以前 | 普通免許 | 8t未満 | 5t未満 | 18歳以上 |
| 大型免許 | 8t以上 | 5t以上 | 20歳以上 運転経験2年以上 |
|
| 平成19年6月2日~平成29年3月11日 | 普通免許 | 5t未満 | 3t未満 | 18歳以上 |
| 中型免許 | 5t~11t未満 | 3t~6.5t未満 | 20歳以上 運転経験2年以上 |
|
| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 21歳以上 運転経験3年以上 |
|
| 平成29年3月12日以降 | 普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 18歳以上 |
| 準中型免許 | 3.5t〜7.5t未満 | 2t〜4.5t未満 | ||
| 中型免許 | 7.5t~11t未満 | 4.5t~6.5t未満 | 20歳以上 運転経験2年以上 |
|
| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 21歳以上 運転経験3年以上 |
上表のとおり、同じ「普通免許」でも、実際に運転できる車両の範囲は取得時期や免許証の記載内容によって異なる場合があります。特に業務でトラックを使用する場合や、就職・転職を考えている場合は、自身の免許証や車検証の記載をよく確認し、不明な点があれば警察署や免許センターに相談することをおすすめします。
参考:公益財団法人 全日本トラック協会「運転免許証と車検証をチェックして運転できるトラックかどうか必ず確認しよう」
公益財団法人 全日本トラック協会「~平成19年6月2日からスタート~ここがしりたい中型免許Q&A」
公益財団法人 全日本トラック協会「平成29年3月からトラックの免許が大きく変わります。-準中型免許Q&A」
普通免許で運転できるトラックの車種例

本章では、普通免許で運転できる主なトラックの車種や特徴について、わかりやすく紹介します。
特に建設現場や配送業、引っ越し業などで使用される小型トラックの中には、現行の普通免許の条件を満たすものと、そうでないものが混在しています。そのため、実際に車両を選ぶ際には、免許条件に合っているかどうかを十分に確認することが重要です。併せて、トラック選定時の注意点も押さえておきましょう。
代表的な車種例
現行の普通免許で運転できる可能性のあるトラックの例として、代表的な小型トラックの車種をいくつか紹介します。以下、一般的に広く知られており、国内で高いシェアを誇るモデルです。
| 車種(メーカー) | 詳細 |
|---|---|
| エルフミオ (いすゞ自動車) |
1.9Lディーゼルエンジン「RZ4E」を搭載し、高い燃費性能と最大積載量1.35tを両立しています。キャビンは広く快適で、乗り降りしやすい設計に加え、小径ステアリングや細かく調整できるシートにより、誰でも運転しやすい環境を実現しています。 |
| 日野デュトロ Z EV (日野自動車) |
コンパクトな4ナンバーサイズながら、荷室容積約8m³、最大積載量1tを実現しています。全高は地下駐車場に対応し、床面地上高400mmの超低床設計により乗降もスムーズです。運転席から荷室へ直接移動できるウォークスルー構造を採用しています。 |
| ダイナ カーゴ (トヨタ自動車) |
「Single Cab Gasoline/2WD」や「Double Cab Gasoline /2WD」などが現行の普通免許で運転できるトラックに該当します。全車に高さ160mmのオープンフレームを採用し、優れたねじり剛性と耐久性を確保しています。振動やノイズを抑える設計により、乗員の疲労軽減にも配慮されています。 |
| アトラス (日産自動車) |
全車に衝突回避を支援する「プリクラッシュブレーキ」を標準装備し、「全車速車間クルーズ」や「レーンキープアシスト」も選択可能です。ドライバーの状態を監視する「ドライバーステータスモニター」や異常時に車両を制御・停止させる「EDSS」も選べるなど、安全性を高めています。 |
これらの車種は一般的に2tトラックと呼ばれていますが、オプションや架装内容によっては車両総重量が3.5tを超え、現行の普通免許では運転できない場合もあります。特に中古車やカスタマイズ車を検討する際は、「自分の持っている普通免許で運転できるかどうか」を販売店に事前確認することが大切です。
参考:いすゞ自動車「いすゞ、国内唯一の普通自動車免許対応の小型ディーゼルトラック「エルフミオ」を発売~ドライバーの裾野を広げる「だれでもトラック」、ドライバー不足の解消に貢献~」
日野自動車「日野デュトロ Z EV(小型BEVトラック)」
トヨタ自動車「トヨタ ダイナ カーゴ 」
トヨタ自動車「カタログ|ダイナ カーゴ 1.0tonシリーズ」
日産自動車「アトラス トラック 普通免許対応モデル」
日産自動車ニュースルーム「新型「アトラス」を発表」
よく使われるタイプ・形状
普通免許で乗れるトラックには、使用目的に応じてさまざまなタイプがあります。以下に、業種ごとに多く利用されている代表的なタイプを紹介します。
| タイプ、用途例 | 詳細 |
|---|---|
| 小型アルミバン (ネットスーパー、宅配便) |
箱型の荷台を持ち、防水性や防犯性に優れた構造で、都市部の宅配業務で広く利用されています。ただし、荷台がフルアルミ仕様になっていたり、断熱材が入っていたりする場合は、車両の重量が増すため注意が必要です。 |
| 小型冷蔵・冷凍車 (食品配送) |
冷凍ユニットや断熱材の搭載により、見た目以上に重量がかさむ傾向があります。たとえ「2t冷蔵車」と表記されていても、車両総重量が普通免許の制限を超えるケースもあるため、事前確認が不可欠です。 |
| 小型平ボディ (建材・資材運搬) |
荷台が平らでシンプルかつ軽量な構造です。木材や足場資材、袋物などの輸送に適していますが、クレーンや架台を後付けすると総重量が増え、普通免許では運転できなくなる可能性があります。 |
| 小型ウイング車 (引っ越し・量販店配送) |
荷室の左右が大きく開閉する構造で、フォークリフトによるパレット積み下ろしがしやすいのが特徴です。便利な反面、ウイング機構による重量増加には十分注意が必要です。 |
たとえ「小型」と分類されるトラックであっても、オプション装備や仕様変更により、普通免許の範囲を超えるケースがあります。運転前には必ず車検証を確認し、「車両総重量」や「最大積載量」が普通免許の条件を満たしているか確認しましょう。
普通免許でトラックを運転する際の注意点
本章では、普通免許でトラックを運転する際の注意点を3つピックアップし、順番に解説します。
車検証の確認は必ず行う
外観が同じでも、型式や装備、荷台の仕様(架装)によって車両の重量が異なります。
普通免許で運転可能かどうかを判断するには、車検証に記載されている「車両総重量」と「最大積載量」を確認する必要があります。外観だけで判断するのは非常に危険です。
無免許運転とみなされる可能性
普通免許の条件を超える車両を運転した場合、たとえ事故を起こさなかったとしても「無免許運転」とみなされることがあります。
これは、運転免許は特定の条件下でのみ有効とされており、その範囲を逸脱して運転することは、制度上「無資格運転」と同等に扱われるためです。運転者に悪意がなかった場合でも、結果として法律違反に問われる可能性があるため、免許の範囲を正確に把握しておくことが重要です。
無免許運転は重大な交通違反に該当し、違反点数の加算や罰金、免許停止といった厳しい処分を受ける可能性があります。
業務利用の場合は企業側の責任も問われる
運送業や建設業などで社員がトラックを使用する場合、会社側にも確認責任があります。運転する社員の免許区分を超える車両を使用させた結果、事故や違反が発生すれば、企業側にも「安全配慮義務違反」や「管理責任」などが問われる可能性があります。
業務で使用する際は、車両と免許の条件を十分に照らし合わせたうえで運用することが重要です。
普通免許と他の免許(準中型・中型・大型)の違い

普通免許で運転できないトラックに対応するため、現行の制度では「準中型」「中型」「大型」といった上位の運転免許が用意されています。
準中型免許は、2017年3月の法改正で新たに設けられた免許区分で、運転できる車両の大きさは普通免許と中型免許の中間にあたります。これにより、若年層でも比較的大きな車両を運転できるようになり、物流業界の人材確保などを目的とした制度変更が行われました。
下表は、各免許の区分と運転可能な車両の条件をまとめたものです。
| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|
| 普通免許 (8t限定付) |
8t未満 | 5t未満 | 10人以下 |
| 普通免許 (5t限定付) |
5t未満 | 3t未満 | 10人以下 |
| 普通免許 (現行) |
3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
| 準中型免許 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | 10人以下 |
| 中型免許 | 11t未満 | 6.5t未満 | 29人以下 |
| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
準中型免許は18歳から取得でき、現行の普通免許よりも幅広いトラックを運転できます。特に宅配業や配送業など、比較的大型の車両を扱う職種を目指す場合におすすめの運転免許です。
まとめ|普通免許で乗れるトラックは「取得時期」がカギ
普通免許で運転できるトラックの範囲は、「車両総重量」「最大積載量」「乗車定員」の3つの条件で決まります。ただし、同じ普通免許でも取得した時期によって条件が大きく異なるため、自分の免許がどの範囲に該当するかを必ず確認することが大切です。
「2tトラックだから普通免許で乗れる」と思い込まず、必ず車検証で「車両総重量」「最大積載量」などの数値をチェックしましょう。もし、普通免許の対象外とされるトラックの運転が必要な場合は、準中型・中型・大型免許の取得も視野に入れることをおすすめします。