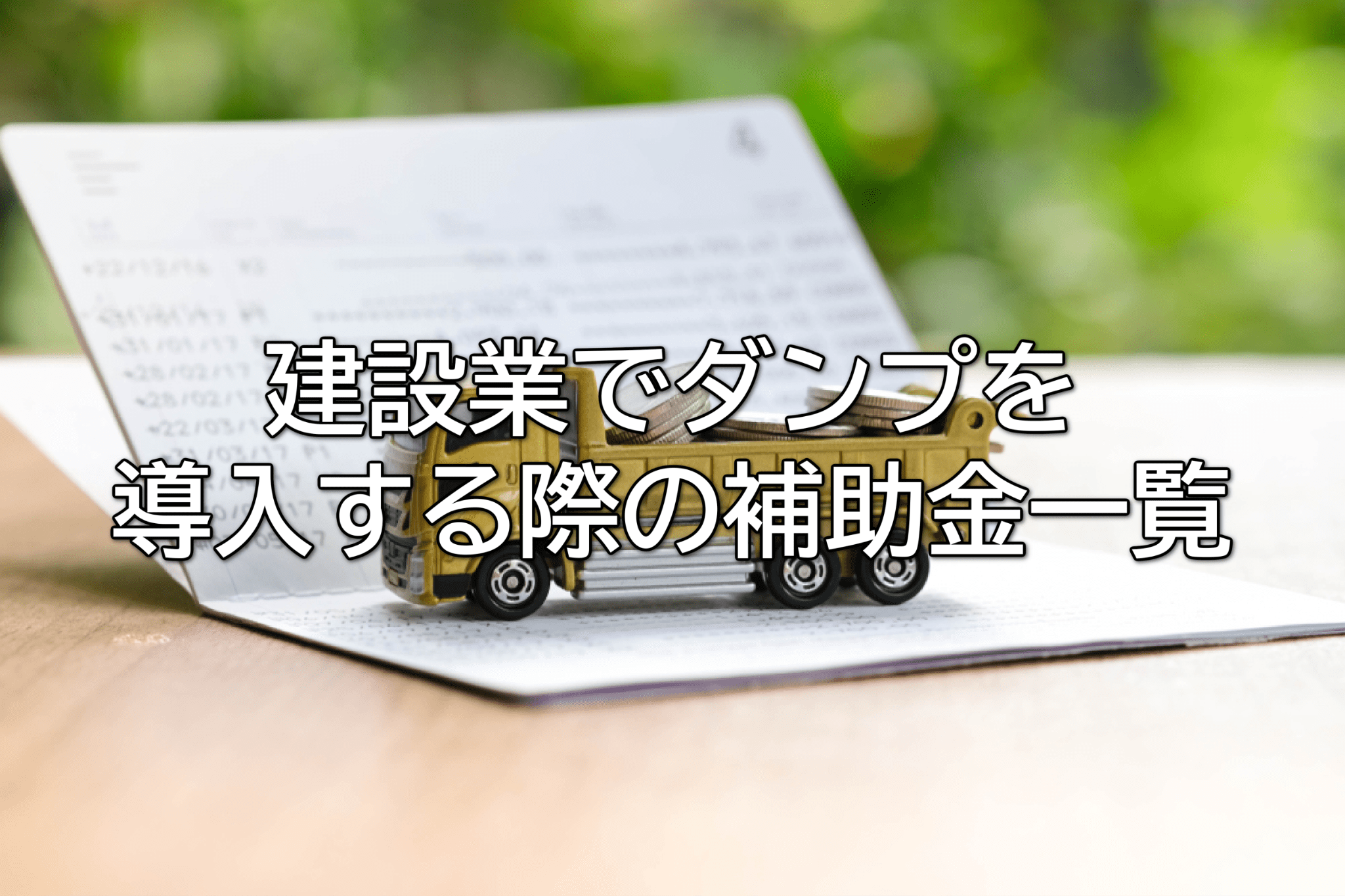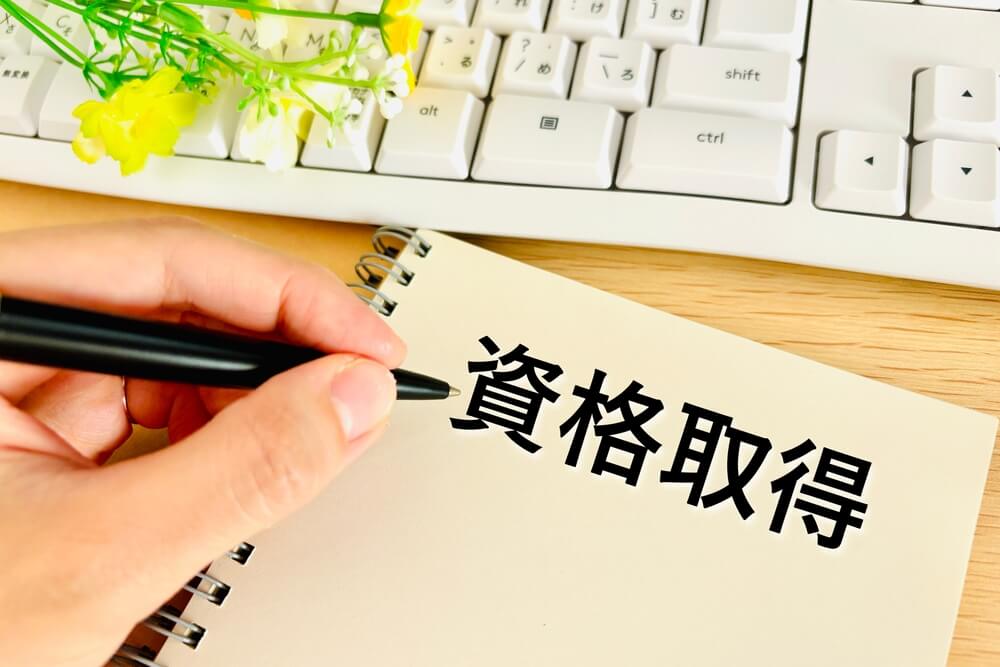ICT施工のメリット・デメリットとは?課題も解説
近年、建設業界ではICT施工の導入が急速に進んでいます。国は「i-Construction」を推進するため、講習や補助金などを通じて建設業者によるICT施工の導入を後押ししている状況です。
ICT施工を導入することで、施工の精度向上・作業時間の短縮・コスト削減など、多くのメリットが得られる一方で、導入コストや運用面での課題も存在します。そのため、ICT施工を導入すべきかどうかを判断するには、メリットとデメリットの両方を正しく理解することが重要です。
本記事では、ICT施工を導入するメリット・デメリットに加えて、導入時の課題や解決策についても詳しく紹介します。ICT施工の導入を検討している建設事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
ICT施工とは?

まずは、ICT施工とはどういったものか、導入前に知っておくべき基礎知識をまとめました。
ICT施工の概要
ICT施工とは、建設業界における情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用した施工プロセスを指します。
具体的には、3D測量技術や建設機械の自動化、クラウドベースの管理システムなどを用いることで、施工の効率化や精度向上を図るものです。従来は手作業に依存していた工程をデジタル化することで、より高精度で効率的な施工が可能です。
活用される建設業界の分野
ICT施工は、以下のような建設分野で活用されます。
| 分野 | 詳細 |
|---|---|
| 土木工事 | 道路工事やダム建設、トンネル掘削など、大規模な土木プロジェクトで施工の効率化と精度向上に貢献している。 |
| 建築工事 | ビルや住宅の建設において、設計から施工管理まで3Dデータを活用し、作業の最適化が図られている。 |
| インフラ整備 | 橋梁工事や上下水道の整備など、公共インフラの建設においても、ICTを活用した効率的な施工が進められている。 |
| 維持管理・点検 | 既存のインフラや建築物の補修・維持管理において、センサー技術やドローンを活用した点検が導入されている。 |
このように、ICT施工は建設業界の幅広い分野で活用されており、より安全で効率的な工事の実現に貢献しています。
以下の記事では、ICT施工を導入するにあたり知っておきたい流れや成功のポイントについて詳しく解説しています。ICT施工の導入を検討している場合には、併せてご覧ください。
ICT施工とは?流れや導入のポイント、問題点をわかりやすく解説
ICT施工のメリット
ICT施工は、情報通信技術を活用し、建設現場の効率化や精度向上を図る方法です。ICT施工の代表的なメリットは、以下の通りです。
- 生産性安定・向上
- コスト削減
- 品質の向上
- 労働力不足の解決
- 安全性の向上
それぞれのメリットについて順番に詳しく解説します。
生産性安定・向上
ICT施工を活用することで、作業時間の短縮や人的ミスの削減、施工精度の向上が可能となり、建設現場の生産性が向上します。また、作業のばらつきが少なくなることで安定化も期待できます。
例えば、ドローンや3Dレーザースキャナーを活用した測量技術により、測量作業の時間を大幅に削減できます。従来の手作業による測量では、天候や作業者のスキルによって所要時間が異なりましたが、ICT施工では標準化された手法で、短時間かつ一定の精度で測量が完了するため、作業時間の予測がしやすくなります。
また、データを活用した進捗管理により、作業の遅れを事前に把握し、適切な対策を講じることが可能です。これにより、突発的な遅延リスクが減少し、工程全体の最適化が図られるため、プロジェクトが予定通りに進行しやすくなります。
このように、ICT施工の導入は、建設現場の生産性を向上させるだけでなく、作業のバラつきを抑えて安定化を促す重要な施策です。
コスト削減
ICT施工を導入することで、作業時間の短縮や人的ミスの削減、資材の無駄の削減といった効果が得られ、施工コストの減少につながります。
具体的には、GNSS(全球測位衛星システム)やセンサーを搭載したICT建機(※)を使用することで、高精度な施工が可能になり、手戻りや再施工の発生を防げます。例えば、ICT施工対応のブルドーザーを使用すると設計データにもとづく自動制御が可能になり、余分な掘削や資材の追加使用を防げるため、コスト削減につながります。
また、クラウド型の施工管理ツールを活用すれば、遠隔で施工状況を確認できるため、管理者が頻繁に現場を訪れる必要がなくなります。施工進捗をリアルタイムで把握し、現場の状況を遠隔で確認できるため、管理業務にかかるコストも削減できます。
※:ICTを活用した建設機械のこと。GNSSやレーザーセンサーなどを用いて、施工の効率化や精度向上を図れる。以下の記事では、ICT建機について詳しく解説しています。
品質の向上
ICT施工を導入することで、精度の高い施工や均一な品質の確保、人的ミスの低減が実現します。
従来の施工では、オペレーターの熟練度によって仕上がりにばらつきが出ることがありました。しかし、ICTを活用すれば、精度の高いデータにもとづいた施工が可能となり、品質の向上が期待できます。
例えば、ICT施工では、ドローンや3Dレーザースキャナーを活用した高精度な測量が可能です。高精度な測量データによって、施工時のズレや追加修正の発生を抑えられ、品質の向上に直結します。
労働力不足の解消
建設業界では、少子高齢化の影響で労働力不足が深刻化しており、人手不足による施工遅延や品質の低下が懸念されています。そこでICT施工を導入することで、省人化や作業効率の向上、新規人材の確保が見込まれ、労働力不足の解消に寄与する施策として注目されています。
例えば、ICT建機の活用や自動化技術の導入により、少ない人数でも施工を進められる仕組みが整います。
また、3D測量や設計データの活用、ICT建機の自動制御によって、作業の効率化が図れます。結果として作業時間を短縮できるので、少人数でも作業の効率的な進行が可能です。
安全性の向上
建設業界では、高所作業や重機操作による事故が多発しており、安全対策の強化が求められています。
ICT施工を導入することで、建機の遠隔操作や自動制御が可能になり、作業員が危険な場所に立ち入らずに施工を進められます。作業員が危険な環境で作業を行う機会を減らせるので、安全性の向上につながります。
また、ICT施工では、GNSSやセンサー技術を活用した自動制御により、建機の誤操作や作業ミスのリスクを軽減できるため、安全性の高い施工につながります。
ICT施工のデメリット

ICT施工は建設業界の効率化や安全性向上に大きく貢献しますが、一方で導入に際し、いくつかのデメリットも存在するので、事前に把握しておくことが大切です。
ICT施工の主なデメリットは、以下の通りです。
- 初期導入コストの大きさ
- 技術習得の難しさ
- システムトラブルのリスク
それぞれのデメリットについて、順番に詳しく解説します。
初期導入コストの大きさ
ICT施工の導入には、多額の設備投資が必要になります。
例えば、ICT対応の重機や測量機器、ソフトウェア、通信設備などの導入が必要になるため、設備投資の初期コストが比較的高額となり、中小規模の建設事業者にとっては慎重な判断が求められます。
技術習得の難しさ
ICT施工は建設現場の効率化や生産性の向上に寄与する一方で、新しい技術の習得には時間とコストがかかるというデメリットがあります。
例えば、従来のアナログな施工管理では、測量や施工計画の調整を紙の図面と口頭のやり取りで行うことが一般的でした。しかし、ICT施工では3Dデータを用いた施工計画や、建機の自動制御などの新しい技術が求められるため、オペレーターはデジタルツールの操作やデータ解析のスキルを身につける必要があります。
特に、ICT建機の操作は、従来の重機と異なり、タッチパネルやGPS連携の設定が必要になるため、未経験者にとっては戸惑うことも多いです。また、施工管理ソフトウェアの活用には、基礎的なITスキルが求められるため、パソコン操作に不慣れな現場作業者にとっては大きなハードルとなります。
そのため、ICT施工を導入する際には、事前に研修を実施し、現場での活用をスムーズにすることが重要です。
システムトラブルのリスク
ICT施工は、デジタル技術を活用して施工の効率化や品質向上を図る手法ですが、一方でシステムトラブルが発生するリスクがあり、現場の進行に大きな影響を与える可能性があります。
例えば、ICT建機の自動制御システムが誤作動を起こした場合、施工精度に影響が出るだけでなく、一時的に作業が停止することもあります。また、クラウドベースの施工管理システムがネットワーク障害で使用できなくなると、進捗管理やデータ共有が滞り、施工の遅延につながるおそれがあります。
さらに、ソフトウェアのバージョンアップや機器の定期メンテナンスを怠ると、トラブルの発生率が高まり、結果として予期せぬコスト増加を招く可能性があります。
そのため、ICT施工を導入する際には、システムの定期的な点検と、トラブル時の対応策を事前に準備しておくことが重要です。
ICT施工の課題
ICT施工の導入には、以下のような課題もあります。
- 中小企業での導入の壁
- 現場とのギャップ(アナログ文化との折り合い)
- データ管理・セキュリティ
- 専門人材の確保
これらの課題を理解し、対策を講じることで、ICT施工をより効果的に活用できるようになります。今後の建設業界においてICT施工の導入が加速することを考えても、課題に早めに対応することが重要です。それぞれの課題について、順番に詳しく解説します。
中小企業での導入の壁
ICT施工には、生産性の向上やコスト削減、品質・安全性の向上といった数多くのメリットがあり、近年では中小企業においても導入の動きが広がりつつあります。
一方で、導入に際しては「初期コスト」や「システム運用」「人材の確保」といったいくつかの課題があるのも事実です。しかし、これらの課題は工夫や外部サポートの活用によって十分に対応可能であり、導入のハードルは以前に比べて着実に下がってきています。
ここでは、中小企業がICT施工を導入する際に直面しやすい課題と、それに対する具体的な対応策をご紹介します。
| 主な課題 | 詳細 |
|---|---|
| 初期導入コストに見合う効果の検討 | ICT建機や3D測量機器、ソフトウェアなどの導入には一定の初期コストがかかります。ただし、最近ではリースやレンタルといった柔軟な選択肢も増えており、段階的な導入も可能です。
また、経済的な効果だけでなく、安全性や職場環境の改善、採用ブランディングなど、非経済的なメリットにも注目することで導入の価値をより明確にできます。 |
| システム運用の体制づくり | ICT施工では、建機の導入だけでなく、ソフトウェアの運用・管理体制を整えることも欠かせません。
特に、ソフトウェアの管理や保守・メンテナンスについては、導入時にしっかりと理解しておくことが大切です。これまでの建設現場ではあまり馴染みのなかった分野かもしれませんが、ICT施工の継続的な活用を見据えれば、機能のアップデートやサポート体制の強化といった恩恵を受けられる可能性もあります。 さらに、クラウド型のシステムを導入したり、外部サポートを活用したりすることで、ITに関する専門知識がなくても無理なく運用できる体制を構築できます。こうした工夫により、社内リソースに過度な負担をかけることなく、ICT施工の安定した運用が実現しやすくなります。 |
中小企業がICT施工を導入するためには、コスト削減やシステム運用の簡略化などの対策が必要です。具体的な対策を以下に示しました。
| 主な対策 | 詳細 |
|---|---|
| 初期導入コストの抑制 | ・ICT施工は、一度にすべての工程へ導入するのではなく、測量や施工管理などから段階的に始めることで、業務との親和性や現場の理解を深めながら、本格導入へとつなげることができます。
・スモールスタートを意識した導入は、社内体制の整備や継続的な活用にもつながりやすく、無理なく実践しやすい点がメリットです。 ・また、国や自治体による補助金・助成金制度を活用できるケースもあるため、最新の公募情報を確認し、戦略的に導入計画を立てることが効果的です。 |
| システム運用の簡略化 | ・クラウド管理型のソフトウェアを利用し、IT管理の負担を軽減する。
・操作が簡単で、中小企業向けのICT施工ツールを選ぶ。 ・ICT施工のトラブル対応、サポートを外部業者に委託する。 |
現場とのギャップ(アナログ文化との折り合い)
建設業界では長年のアナログ文化が根付いており、ICT施工の普及には大きなギャップがあるのが実情です。特に、中小企業や経験豊富なベテランのオペレーターが多い現場では、ICT施工の導入に抵抗感があるケースが少なくありません。
ICT施工をスムーズに導入し、現場とのギャップを解消するためには、以下のような対策が効果的です。
| 主な対策 | 詳細 |
|---|---|
| アナログ文化との共存 | ・初期段階では、紙の設計図と3Dモデルの両方を活用する。
・ICT施工の運用にあたり、現場技術者の意見を積極的に取り入れる。 ・ドローン測量やタブレットを活用した施工管理など、導入しやすいICTから取り入れる。 |
| 現場環境の整備 | ・クラウド管理を導入するため、現場にWi-Fiやモバイル通信環境を整備する。
・現場オペレーターでも扱いやすいソフトウェア、アプリを導入する。 |
データ管理・セキュリティ
ICT施工では、3D測量データ・施工計画・進捗管理情報など、大量のデジタルデータを扱います。これらのデータを適切に管理し、セキュリティ対策を講じることは、業務の効率化だけでなく、情報漏えいや不正アクセスを防ぐ上で非常に重要です。
しかし、データの管理方法やセキュリティリスクへの対応は、ICT施工の普及において大きな課題となっています。データ管理やセキュリティのリスクを軽減するためには、以下のような対策を実施することが有効です。
| 主な対策 | 詳細 |
|---|---|
| データの適切な管理 | ・クラウドを用いてプロジェクトごとにデータ管理システムを導入し、情報の分散を防ぐ。
・権限設定を明確にし、必要な人だけがデータを閲覧・編集できるようにする。 ・データ消失に備え、自動バックアップ機能を活用する。 |
| セキュリティ対策の強化 | ・システムやクラウドにログインする際に追加の認証ステップを設け、不正アクセスを防ぐ。
・VPN(仮想プライベートネットワーク)やSSL(暗号化)通信を活用し、安全なデータ通信を確保する。 ・セキュリティ意識を高めるために、定期的な情報セキュリティ研修を実施する。 |
| ソフトウェア・システムの最適化 | ・データフォーマットを統一して異なるツール間での互換性を確保し、スムーズなデータ共有を実現する。
・システムやソフトウェアの定期的な更新を徹底し、脆弱性を防ぐ。 |
専門人材の確保
ICT施工を効果的に活用するためには、測量技術・データ解析・機械制御・BIM/CIMなど、多岐にわたるスキルを持つ技術者が必要です。しかし、こうした専門知識を持つ人材が不足しており、多くの企業がICT施工の導入に苦労しているのが現状です。
専門人材の確保を進めるためには、業界全体での人材育成と企業の採用戦略の強化が重要です。具体的には、以下のような対策が求められます。
| 主な対策 | 詳細 |
|---|---|
| 社内研修・教育制度の充実 | ・ICT施工に関する研修を定期的に実施する。
・ベテラン技術者向けのICT習得プログラムを導入する。 ・ICT施工の実務経験を積めるOJT(現場教育)を実施する。 |
| IT・デジタル技術者の採用強化 | ・IT業界出身者を積極的に採用し、建設業界への転職を促す。
・異業種(例:IT企業)からの人材採用を検討する。 ・リモートワーク可能な職種を増やし、柔軟な働き方を提供する。 |
ICT施工の今後の展望

ICT施工は、建設業界の生産性の安定化・向上や労働力不足の対策として注目されており、今後ますます普及が進むと予想されます。国土交通省もICTの活用を推奨しており、特にインフラ整備や公共工事では、工種によってはICT施工の導入が推奨・指定されるケースも増えており、今後さらに広がっていくと見られます。
本章では、「国の支援策」と「今後の技術革新」という2つの観点からICT施工の今後の展望について解説します。
国の支援策
ICT施工の普及には、国の支援が不可欠です。国土交通省は「i-Construction」政策の一環として、ICT施工の導入を積極的に推進しています。
この政策は、建設業の生産性と安全性の向上を目的としたもので、具体的には公共工事へのICT施工の導入義務化や、補助金制度の整備が進められています。補助金や助成金の活用によって、中小企業でもICT施工を導入しやすい環境が整いつつある状況です。
今後も支援策の拡充や技術革新が進むことで、ICT施工の導入ハードルが下がり、より多くの建設事業者がICTを活用できる環境が整っていくものと見られます。
i-Constructionの取り組みについて理解を深めたい場合は、以下の記事をご覧ください。
i-Constructionとは?国交省が推進する最新2.0も解説
今後の技術革新による可能性
ICT施工の対応範囲や導入メリットは、技術革新によって拡大を続けています。特にAI(人工知能)、5G通信、BIM/CIM、クラウド技術の発展が、今後のICT施工の可能性を広げる重要な要素となっています。
例えば、AI技術の進化によって施工の自動化が加速し、作業の精度向上や人手不足の解消につながる可能性があります。AIを搭載した重機の導入が進めば、オペレーターの負担を軽減しながら精度の高い施工が可能となるでしょう。
また、5G通信の普及により、高精度のリアルタイムデータを活用した施工管理が可能になります。遠隔施工が普及すれば、過酷な環境での作業が減り、労働環境の改善にもつながるでしょう。
まとめ
ICT施工は、生産性・品質・安全性の向上、コスト削減、労働力不足の解消といった多くのメリットをもたらす手法です。
一方で、初期導入コストに対する、導入の目的や効果の検討、どのように使い込んでいくかといった実装イメージを持つこと、保守メンテナンスなどの理解、データ管理・セキュリティの課題など、導入時に検討しておくとより導入メリットを得られる検討課題も存在します。
今後は、AI・5G・BIM/CIM・クラウド技術の進化によって、ICT施工の導入障壁が下がり、より多くの企業が活用しやすくなることが予想されます。また、国の支援策や補助金の活用も、導入の大きな後押しとなると見込まれます。
企業がICT施工を効果的に活用するためには、自社における導入メリットを把握した上で、最新の技術動向をキャッチしつつ、積極的に導入を進めることが重要です。今後とも、新技術の進化を見据えた戦略的なICT施工の導入が、採用面でのアドバンテージや経営面での競争力向上につながるでしょう。