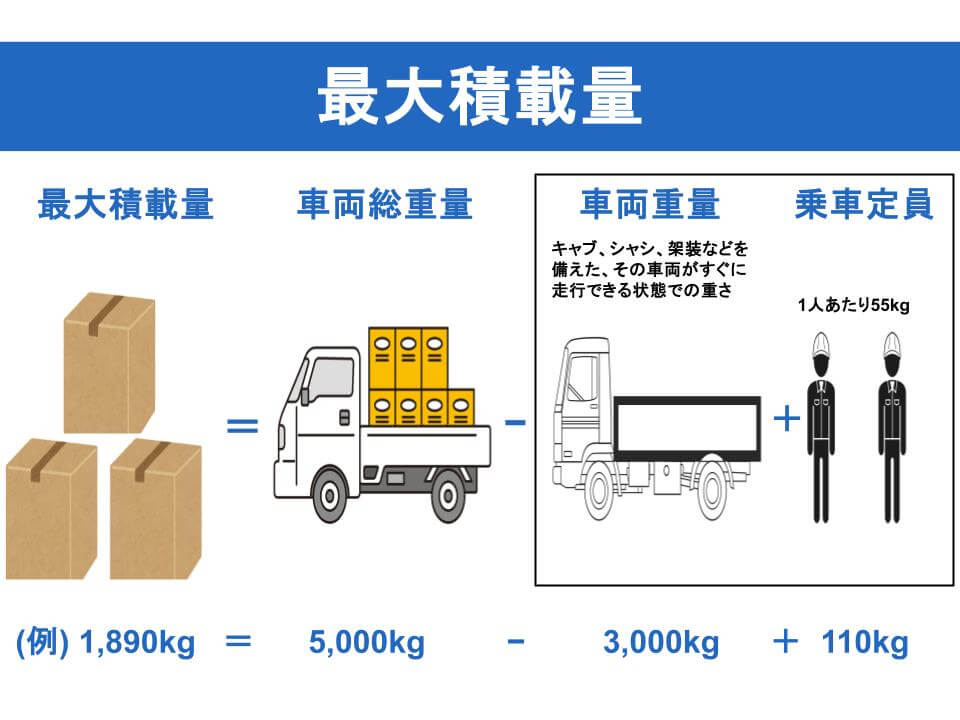ダンプ荷台の名称を写真で解説|各部位の役割と名称一覧
ダンプトラックの荷台は、ただの鉄製の箱ではなく、安全性や積載効率、作業のしやすさ、メンテナンス性を確保するために、多くの部品が組み合わされて構成されています。
本記事では、建設現場の担当者や整備に携わる方々にとっても実用的な視点から、ダンプ荷台の各部名称とその役割について詳しく解説していきます。
ダンプトラックの基本構造や種類をまだ確認していない方は、先に以下の記事を読むと理解が深まります。
ダンプトラックとは?特徴・用途・必要な免許をわかりやすく解説
目次
コボレーン(飛散防止装置)

コボレーンとは、ダンプトラックの荷台後部に取り付けられる幕状のパーツで、主に砂利や砕石などの飛散を防ぐための装置です。荷台を傾けたときや走行中に積載物が飛び出すのを防ぐ役割を果たします。
一般的には、荷台後端の上部にボルトで固定されており、素材には柔軟性と耐久性を兼ね備えたゴムやターポリンが使用されています。最近では、キャビン内から操作可能な電動巻き取り式のモデルも増えています。
コボレーンが破損していたり、めくれていたりする状態では、本来の飛散防止効果が期待できない点に注意しましょう。また、荷物を過剰に積載すると、コボレーンが押し上げられて機能しなくなる場合があります。
一部の地域や運搬する荷物の種類によっては、コボレーンの装着が求められる場合があります。未装着のまま走行した場合、指導や注意を受けることも考えられるため、事前に自治体や取引先のルールを確認しておくと安心です。
足かけ(荷台ステップ)

足かけとは、作業員が荷台に上がる際に使う踏み台のような構造で、小型から大型ダンプまで広く設置されています。多くの場合、車両の側面下部に取り付けられており、安全に昇降するための補助設備です。
ステップの材質には鉄やアルミが使われており、格子状または板状の形状が一般的です。踏み面には滑り止め加工が施されており、作業中の転倒リスクを軽減します。
足かけの主な使用場面は、以下のとおりです。
- 荷物の確認や清掃作業
- 荷台へのシート掛けやロープの固定
- 点検や整備などで荷台に乗る際
足かけを使用する際、雨や泥で濡れていると滑りやすくなるため、足元を十分に確認してください。また、ステップが変形していたり、溶接部分に劣化が見られたりする場合は、早めの修理が必要です。
安全な作業環境を保つためにも、定期的な点検とメンテナンスを心がけましょう。
プロテクタハシゴ(はしご/サイドラダー)

プロテクタハシゴとは、荷台への昇降をより安全に行うために設計された縦型のはしごです。足かけよりも高さがある場面での使用に適しており、作業者の安全確保に大きく貢献します。
素材は主に鋼材やアルミが使われており、各ステップには滑り止め加工が施されています。車両によっては、固定式や折りたたみ式、引き出し式など、使用状況に応じた構造が採用されています。
プロテクタハシゴは荷台上での高所作業時に、安全な昇降手段として役立ちます。荷崩れ防止ネットの取り付けや、積載物の固定作業時にも活用されます。また、安全帯を引っ掛けられるフックなどが近くに備えられている場合も多く、より安全に作業ができます。
しかし、プロテクタハシゴを使用する際、雨や雪などで濡れていると、非常に滑りやすくなるため慎重な昇降が必要です。長期間使用していない場合はサビや破損がないか定期的に点検し、必要に応じてメンテナンスを行いましょう。
サイドガード

サイドガードは、歩行者や自転車の巻き込み事故を防ぐために車体の側面下部に取り付けられる横方向の保護バーです。走行中の安全性を高める上で、非常に重要な役割を担っています。
一定の貨物自動車には、法令によりサイドガード(巻込防止装置)の装着が求められています。特に、車両総重量が8t以上または最大積載量が5t以上の大型貨物自動車は、地面からの高さやタイヤとの間隔など、厳格な装着基準が設けられています。
※普通型貨物自動車のうち、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のものは、原則として大型扱いとなり、サイドガードの装着が必要となる場合があります。
実際の扱いや義務の適用範囲については、車両の使用目的や運輸局の指導内容によって異なることがあるため、必ず管轄機関で確認してください。
材質は主に鋼管やアルミ製のパイプで、ボルトで車体に固定されるのが一般的です。また、一部の車両では、ステップや工具箱と一体化した構造になっていることもあります。
サイドガードに関して、バーの変形や溶接部分の割れ、固定の緩みがあると重大な事故につながるおそれがある点に注意が必要です。定期的に高圧洗浄などで汚れやサビを取り除き、点検を行いましょう。
参考:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】」
アオリ(前・横・後)

アオリとは、荷台の前後左右を囲む鋼製のパネルで、積荷の落下や飛び出しを防ぐ重要な部品です。多くの車両では開閉式になっており、荷物の積み降ろしをスムーズに行う上で欠かせない構造です。
下表に、各部の名称と役割をまとめました。
| 名称 | 特徴 |
|---|---|
| 前アオリ | キャビン側を守る固定式のパネル |
| 横アオリ | 側面にあり、開閉や脱着が可能なヒンジ式 |
| 後アオリ | 後方にある開閉パネルで、荷降ろしの主役 |
主な開閉方式として、跳ね上げ式(上方向に持ち上がる)や観音開き式(左右に分かれて開く)などがありますが、他にも自動ロック式や油圧式など、車両や用途に応じてさまざまな方式が採用されることがあります。
積荷がアオリを押していると、開閉が困難になる場合がある点に注意しましょう。また、ヒンジやロック機構の不具合は事故につながるおそれがあるため、定期的な点検と整備が重要です。
鳥居

鳥居とは、トラックの荷台とキャビンの間に設けられた縦型の金属フレームで、万が一積荷が前方にずれた際に、運転席を保護する「防護壁」のような役割を果たします。
一般的には溶接や一体成型によって取り付けられており、軽量でありながら十分な強度を備えた構造が主流です。また、網状のタイプであれば、後方の視界を妨げず安全性にも配慮されています。
ロープを固定できるフック付きモデルもあり、荷物の固定に便利です。高さのある荷物に対応するため、鳥居上部に補助フレームを追加できる仕様もあります。このように、積載物や用途に応じて機能を拡張でき、安全性と作業効率の両立が図られています。
ホイスト機構(油圧シリンダー)

ホイスト機構とは、荷台を油圧の力で持ち上げ、積荷を効率よく排出するための昇降装置のことです。車両の前方や中央に設置された油圧シリンダーが伸び縮みすることで、荷台を傾ける仕組みになっています。
ホイスト機構には、以下のような種類があります。
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| テレスコピック式 (多段式) |
テレスコピック式(多段式)は、油圧シリンダーが段階的に伸びる構造で、コンパクトながら高い角度まで荷台を傾けることができます。 荷台を効率よく持ち上げるだけでなく、装置自体が省スペースであるため、車両の全長が限られる狭小な現場にも適しています。 |
| スカイフック式 | 堅牢な構造で、大型ダンプなど高負荷の用途に向いています。 |
| ダンプアップ式 | 比較的簡易な構造で、小型トラックによく用いられます。 |
ホイスト機構は油圧漏れやシリンダーの劣化が起こると、動作に支障をきたす恐れがあります。日常点検で油圧の異常やシール部の状態を確認しましょう。また、荷台が上がっている間は、原則としてその下に立ち入らないようにしましょう。やむを得ず作業が必要な場合は、必ず安全棒(サポートロッド)を正しく使用し、安全を十分に確認した上で行動してください。
ヒンジ

ヒンジは、アオリやテールゲートを開閉するための回転支点として機能する重要な部品です。これにより、スムーズな開閉が可能になり、荷物の積み下ろし作業を効率化します。
通常、アオリ1枚につき2〜3か所のヒンジが取り付けられており、強度が求められるため頑丈な鋼材で作られているのが特徴です。また、回転部にはグリスアップが必要な箇所も多く、定期的なメンテナンスが欠かせません。
片側のヒンジが緩んでしまうと、アオリが傾いて正しく閉まらなくなるおそれがあります。また、雨水などでヒンジの軸部が錆びつき、動きが固くなった状態で無理に開閉しようとすると破損の原因にもなります。小型車両では「蝶番」と表記されることもあります。
メインフレーム

メインフレームは、荷台とシャーシをつなぐトラックの基幹構造であり、デッキやアオリを支える「骨組み」となる重要な部品です。
通常、高張力鋼を用いたU字型または箱型断面のフレーム構造が採用されており、走行中の衝撃やねじれ、振動を効果的に吸収するよう設計されています。
メインフレームに関して特に注意すべきポイントは、以下のとおりです。
- 溶接部分の強度が非常に重要で、ひび割れ(クラック)があると車検に通らない可能性があります。
- 重量バランスにも大きく影響するため、フレームの補強や改造を行う際は、構造への負荷を十分に考慮する必要があります。
安全棒(サポートロッド)

安全棒は、ダンプの荷台を持ち上げた状態で点検や整備を行う際に使用する、安全確保のための支え棒です。油圧システムに万が一のトラブルが発生し、荷台が突然降下するのを防ぐ役割を果たします。
安全棒の代表的な使用シーンは、以下のとおりです。
- 荷台下にあるホイスト装置の点検
- 油圧ホースや電装系配線などのメンテナンス時
主にスチール製のバーやピンを所定の固定穴に差し込んで使用します。脱落防止のためにロックピンで確実に固定してください。差し込みが不完全な状態では非常に危険なため、使用前に必ず正しく固定されていることを確認してください。
デッキ(点検用ステージ)

デッキとは荷台の底面全体を指し、土砂・砂利・建設資材などの積み荷を直接受け止める部分です。積載物が滑る際の摩擦やショベルカーなどで積み込む際の強い衝撃に耐えられるよう、非常に頑丈に設計されています。
デッキを使用する際は、以下の点に注意しましょう。
- 積雪地域ではデッキが凍結し滑って転倒する危険性があるため、使用前の確認を徹底しましょう。
- 工具や部品の一時的な置き場として活用されることがあり、整理整頓も重要です。
特に鉄製のデッキは水分や積荷の影響で錆びやすいため、耐久性を維持するには定期的な清掃とメンテナンスが欠かせません。
その他の荷台関連パーツ
ダンプの荷台には頻繁に目にするものの、一般的にはあまり知られていない補助パーツもあります。本章では、その機能と用途を簡単に紹介します。
ダンプ上部受(じょうぶうけ※上部を押さえる固定金具の俗称)
アオリを閉じた際に上部を固定する金具で、走行中の揺れやガタつきを防ぐ重要なパーツです。一部のモデルではロック機構と連動しており、確実な固定が可能です。荷重による変形が起こりやすいため、定期的な点検と交換が欠かせません。
下部シャフト
主に横アオリの回転軸として機能する部品で、アオリの開閉動作をスムーズに行うための支点となります。ヒンジと連動して動作する構造のため、使用頻度が高いと摩耗やガタつきが起きやすく、早めの整備対応が求められます。
蝶番(ちょうつがい)
蝶番(ちょうつがい)は、ヒンジと同様の役割を持つ可動部品で、現場やメーカーによって呼称や使い分けが異なる場合があります。特に小型ダンプやアルミ製アオリなどでは「蝶番」と呼ばれることが多い傾向です。
構造上の役割はヒンジと同じく開閉の回転軸を担っており、摩耗やゆるみが発生しやすいため、グリスアップやボルトの増し締めが必要な点も共通しています。
中間金具
荷台やアオリの途中に取り付けられる補助的な固定金具(支持金具)の総称です。蝶番と蝶番の間に設けられ、補強や変形防止の役割を担います。特に荷重がかかりやすい部分に配置されますが、破損や緩みに気づきにくいため、定期的な点検が重要です。
コンテナパーツ(着脱式ダンプ専用)
コンテナパーツ(着脱式ダンプ専用)は、産業廃棄物運搬車や農業用ダンプなど、荷台(ボディ)を車体から着脱できる構造を持つダンプで使用される専用パーツ類です。
一般的な固定式ダンプでは荷台とシャーシが一体構造になっていますが、着脱式ダンプでは荷台を取り外して交換・整備が可能です。そのため、以下のような着脱を支える専用パーツが備えられています。
- フックロック:荷台とシャーシの固定に使用
- ガイドローラー:着脱時のスムーズな移動を補助
- アウトリガー(着脱脚):荷台の安定支持を確保
これらのパーツも車両の安全性や作業効率に大きく関わるため、日常点検を欠かさず行うことが大切です。
荷台を長く使うためには、定期的な整備や塗装メンテナンスも欠かせません。ダンプ全体の寿命や買い替えの目安については、以下の記事で詳しく解説しています。
ダンプの耐用年数とは?減価償却・買い替え目安・寿命を延ばす方法
以上、ダンプの荷台の各部名称とその役割について解説しました。「ダンプにはどのようなタイプの車両があるのか知りたい」「自社にとって適した種類のダンプが知りたい」といった場合には、併せて以下の記事もご覧ください。
まとめ
ダンプの荷台は、アオリやボディといった目立つ部分だけでなく、金具・軸・固定具・補強パーツといった細かな部品によって、安全性や耐久性が支えられています。
それぞれのパーツが持つ役割や特徴を把握しておくことで、ダンプの構造的な違いや特性が理解しやすくなり、現場の作業内容や運ぶ荷物に適した車両を的確に選べるようになります。
こうした補助部品の状態や仕組みを把握しておくことは、故障や事故の未然防止にもつながり、安全で効率的な作業環境を保つ上で重要です。ダンプを長く安心して使い続けるためにも、荷台の構造を十分に理解しておくことをおすすめします